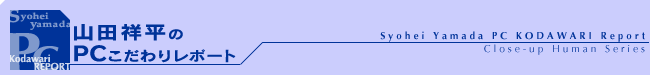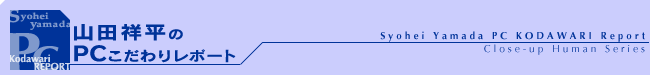| |
 |
どんなに優れたハードウェアがあっても、それを生かすためのソフトウェアがなければ仕方がない。PCIボードタイプとして、初めてハードウェアMPEGエンコーダを搭載し、従来製品に対して大幅な機能拡張を果たしたSmartVision HG/V。今回は、そのソフトウェア部分を含む商品企画を担当した安達政仁(NECカスタムテクニカBB&M開発本部メディアソリューション開発グループ)に話を聞いてみた。
 |
業界標準のファイル形式にこだわりたい |
 「SmartVisionは、録画した映像を.m2pという拡張子のファイルに保存します。これはMPEGファイルそのものですね。さらに、それとは別に.sviという拡張子のファイルを生成します。こちらは、管理用ファイルで、タイトル情報とシーンインデックスを含んでいます。だから、パワーユーザーであれば、m2pファイルを、OSのファイルとしてハンドリングして、好きにしていただいても大丈夫なんです。 「SmartVisionは、録画した映像を.m2pという拡張子のファイルに保存します。これはMPEGファイルそのものですね。さらに、それとは別に.sviという拡張子のファイルを生成します。こちらは、管理用ファイルで、タイトル情報とシーンインデックスを含んでいます。だから、パワーユーザーであれば、m2pファイルを、OSのファイルとしてハンドリングして、好きにしていただいても大丈夫なんです。
特殊なフォーマットは絶対にいやだったんですよ。確かに、初代のSmartVisionは、独自形式のファイルフォーマットを使っていましたから、その印象が強くて、ユーザーの方に誤解を与えている部分があるんですが、決してそうではありません。
大事なことは、こうした標準的な形式のファイルを、いかに、わかりやすく、使う側の人に操作してもらうかということだと思います。それが、アプリケーションのユーザーインターフェースの役割です。
たとえば、SmartVisionでは、ほんの数ステップの操作で、一般のプレーヤーで再生できるDVDが作れます。それが今後の流れだと思いますよ。すごいことが、本当に簡単にできてしまわないといけないんです。 |
|

 |
|
| その過程では、タイムシフトで録画したときの1分単位の細切れファイルをマージしたり、あるいは逆に巨大なファイルを分割したりといったことをするんですね。でも、画質はいっさい劣化しません。これを手作業でやるのはたいへんですよ。画質が劣化することがないなら、手でファイルをハンドリングできるだけの技術や知識を持ったパワーユーザーも、アプリケーションを使ってくれるんです。われわれは、それを目指さなければならないんです」 |
|
 |
ソフトウェアが目指すもの |
安達はたとえハードウェア製品であったとしても、それがソフトから見て使いやすいものでなければならないと考えている。かつては、アマチュア無線などに夢中だった少年が、大学に入って初代PC-9801を購入、プログラミング言語のパスカルなどに取り組み、その流れでNECに入社、以来、ソフトウェア一辺倒で過ごしてきた。入社後は、ずっとOSを担当し、PC-9800シリーズ用のWindows 95のリリースにも立ち会った。
PC98-NXシリーズは、あのキューハチが、IBM PC/ATアーキテクチャに移行することになる記念すべき製品だが、それに装備されたUSBキーボードを制御するWindows用のデバイスドライバも、彼の手によるものだ。
ちなみに、安達がSmartVisionに関わるようになったのは、2001年の7月からだ。同シリーズでは、ネットワークに接続できるスタンドアロン形式のHDレコーダ、SmartVision HD40の原型は安達の企画だ。残念ながら、すでに出荷が終了しているが、今後のHDレコーダが、どのようにあるべきかを示唆し、各方面からの注目を浴びた製品だ。
「SmartVisionには、メディアマネージャーとしての役割を担う、SmartGalleryというソフトウェアが添付されています。PC98-NXシリーズができて、PC-9800専用のWindowsがいらなくなった。OSの仕事はもういい。これからはメディアサーバーの時代だから、時代を先取りする何かおもしろいものを企画しろ、と言われたんですね。自分は、そちら側からSmartVisionという製品を見ていました。HD40もその流れの中にある製品だったんです。今回のHG/Vは、画質の向上のために、小野寺が極限までがんばってくれましたから、次は、自分がソフトウェアでもっとがんばる番ですね。自分自身のこだわりの範囲がまだ十分に入っているとはいえないし、ソフトウェアは、まだまだ使いやすくしなければならないと思います。そのこだわりが完成するまでは、あと2年とか3年かかるかもしれません」
アプリケーションのユーザーインターフェースを完成させるのには、途方もない時間が必要だ。今回の大きなテーマは画質の向上とDVDへの対応で、それは満足できるレベルに仕上がった。だが、安達はまだまだやるべきことがあると考える。
「新しい機能の便利さは、製品を作っている我々自身がいちばんよく知っています。ですから、新製品ができるたびに、それだけをアピールしがちです。例えば、TVチューナボード製品では他にないと思いますが、HG/Vならデスクトップパソコンに録画したビデオを、無線LANでつないだノートパソコンに飛ばして、家の中の好きな部屋で見る、といった使い方ができます。でも、これはパソコンを複数お持ちのお客様でないと、意味がないわけです。いろいろなお客様に製品の良さをご理解していただくためには、従来からある機能も常に新鮮な角度でアピールし続けないといけませんね。
使いやすさの点では、今のユーザーインターフェースは、どちらかというとマニア向けかもしれません。テレビとPCが同等の時代なんですから、そういう時代に合わせて、努力して勉強してもらわなくても、誰でも楽しいことが簡単にできなくちゃいけません」
 今回のSmartVisionには、スリムモードと呼ばれる表示画面が用意された。ウィンドウから余分な要素を省き、できるだけデスクトップ上で邪魔にならないようにテレビを視聴できるようにしたモードだが、安達はそのウィンドウ内のパーツ配置にもとことんこだわった。エンコーダがハードウェアになったことで、プロセッサの負荷が減り、テレビのながら視聴も以前より楽にできるようになったことが、このモードの必要性を高めたのだ。機能の追加は新しい使い方を生み、そしてさらなる機能の追加が必要になる。しかし、機能は単純に追加すればよいというものでもない。機能をつければよいという話でなく、その背景には、なんらかの必然性があるのだ。 今回のSmartVisionには、スリムモードと呼ばれる表示画面が用意された。ウィンドウから余分な要素を省き、できるだけデスクトップ上で邪魔にならないようにテレビを視聴できるようにしたモードだが、安達はそのウィンドウ内のパーツ配置にもとことんこだわった。エンコーダがハードウェアになったことで、プロセッサの負荷が減り、テレビのながら視聴も以前より楽にできるようになったことが、このモードの必要性を高めたのだ。機能の追加は新しい使い方を生み、そしてさらなる機能の追加が必要になる。しかし、機能は単純に追加すればよいというものでもない。機能をつければよいという話でなく、その背景には、なんらかの必然性があるのだ。
「SmartVisionは機能が盛りだくさんになりましたから、これ以上、何か追加しようと思うと、使い易さが犠牲になってしまう可能性も出てきました。お客様からも、ボタンが小さいとか、枠の飾りは要らない、など、たくさんの貴重なご意見をいただきました。今回は高画質とDVD作成を最優先にしたので、ソフトウェア側のユーザインターフェースは、飾りなしのスリムモードを追加する程度となってしまいましたが、実は昨年から細々とですがかなりの時間をかけて大幅に見直し、こだわり開発を進めています。
たとえば、ニュース番組を録画しておくと、トピックだけを勝手に抽出して短時間で内容を把握できる要約視聴は、SmartVisionならではの機能です。忙しいビジネスピープルが、夜、帰宅して、風呂上りのビールを1本楽しみながら今日の出来事を把握してしまい、あとの時間をたっぷりと趣味にあてる、というライフスタイルにはうってつけですよね。ただ、現時点では、ニュース番組でなければ、うまく要約できない場合があるんです。でも、今後はスポーツのハイライトシーンや、音楽番組のアーティストごとのシーン、あるいは曲だけを自動的に抽出するといった応用を考えています。本当に実用になる技術ができるかどうか、NEC関連の研究所の力を借りながら実現に向けて作業をすすめています。
新しいソフトウェアができたら、これまでのハードウェアで使える機能だけでも、既にSmartVisionを使っていただいているお客様に提供したいですね。
先進技術を駆使したBSデジタルも含め、かなりの人数の技術者がこだわり開発に日夜専念しています。その成果をお手頃な価格でサービスできるように、お客様が必要とする機能だけ購入して追加できるようにするのが理想です」
|
 |
技術者のこだわりとハードウェアの完成度 |
ハードウェア的に、すでに、SmartVisionは、調整用に使う素材探しに困るほど画質が向上しているという。DVテープに録画した映像で発生するノイズでさえ評価の邪魔になるというのだから、かなりのレベルにあることは想像に容易い。
実は、ハードウェアを担当した小野寺からも、SmartVisionの基板に搭載されたチューナーユニットに関する新たなエピソードを聞いた。
「大きなチューナーほど性能がいいはずなんですね。ただ、ノートパソコンに内蔵しても、優れた画質を確保したいし、できれば、コスト的にも拡張カードと共通の部品を使いたいというのがホンネです。
チューナーにとって大事なのは、その感度、自動制御のレンジ、そしてアナログデジタル変換の部分なんですが、ハイインピーダンス受けではノイズの影響を受けやすいし、ローインピーダンス受けでは信号のレベル管理が難しくなります。
今のチューナーを実装してみて、最後の最後までどうしても解決できなかったのが、このノイズなんですが、最終的に、自分でユニットがノイズを発生している部分を見つけました。でも、そのクレームをOEM元に要望しても、わかってもらえなかったんですよ。どこがいけないんだって(笑)。
結局、自分で回路を組んで、何もいわずに、こういう仕様にしてくれということで落ち着きました。基板を見るとわかりますが、四角い部品がいくつかあるでしょう。これはローパスフィルタなんですが、中身はコイルとコンデンサーです。これでカットしておかないとノイズが出てしまうんですよ。だから、SmartVisionでは、DA変換のうしろで、このフィルタを通しています。その整合性をとるために、OEM元には仕様を変更してもらいました。3次元Y/C分離のためにいったんアナログに戻しているからなんですが、他社製品ではデジタルのままで処理しているようですね」 |
 |
楽しいことを簡単に |
 安達も小野寺も、ここまでくると、あとは画質に対する好みの世界かもしれないと笑う。あのメーカーのあの製品と比べて、どちらが優れているかということではなく、どちらが好きかという問題になってくるというのだ。そこには、関わったエンジニアの嗜好が強く反映され、メーカーごとの画像となってユーザーの目に映る。 安達も小野寺も、ここまでくると、あとは画質に対する好みの世界かもしれないと笑う。あのメーカーのあの製品と比べて、どちらが優れているかということではなく、どちらが好きかという問題になってくるというのだ。そこには、関わったエンジニアの嗜好が強く反映され、メーカーごとの画像となってユーザーの目に映る。
安達はいう。
「その高画質を、どう見せるか、どう楽しんでもらうかなんですよね。編集もデジタルならラクなんですから、それをもっと楽しんでもらいたいじゃないですか。ケーブルテレビで放送されているようなビデオクリップの番組を丸ごと録画して、カラオケでうたいたい曲だけをピックアップして、ベスト100のDVDを作るような作業を簡単にできるようにしたいですね。まあ、実は、自分がそういうことをやりたいだけなんですけど。今だと、シーンエクスポートを使うか、編集アプリに食わせるかというところなんですが、それなりに手間はかかります。
とにかく、やりたいことは山ほどあって、夢は果てしない、というところです。一つ一つ完成して製品にしていきますが、社内ではいつできるのか、はやくしろ、と叱られてばかりです。なにしろ、こだわり開発で良いものを作りたいですから」
製品を開発するには、常に、コスト意識を持ち続けなければならないことは、小野寺の話を聞いても強く伝わってきた。ただ、ハードウェアエンコードがよいのはわかっていても、そのコストは無視できる額ではない。目下の彼らの悩みは、比較的処理能力の低い廉価なパソコンでこそ、ハードウェアエンコードの力に頼らなければならないのに、コストの関係でソフトウェアエンコードを使わざるを得ないという点だ。
こうしたテーマを、彼らはどう解決するのか。安達と小野寺。とことんこだわる技術者が創るSmartVisionが、この先、描く画に期待が高まる。 |
|
 |
|