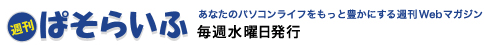 |
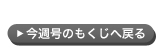 |
 |
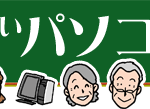 |
 |
|
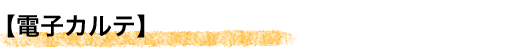 |
|
最近の病院では、机の上にパソコンを置いて、入力しながら診察する先生がいたりします。こういった病院で導入されているのが「電子カルテ」。これまで、紙に書かれていた診療記録を、電子情報として管理しているんですね。 病院でやりとりされる情報は、たくさんあります。問診、診察の所見、各種の検査のオーダーと結果、レントゲンやMRIなどの画像、薬の処方箋、そして会計まで。紙で管理していると、分厚い個人ファイルになってしまいます。 こういった情報を電子化するメリットは、いくつもあります。まず、分厚いファイルが必要なくなること。持ち運びがなくなり、紛失することもありません。病院では、医師法でカルテを5年間保管しなくてはいけませんが、その保管場所も必要なくなります。 また、テキスト化された診察内容がデータベースにはいりますから、過去の症例の検索やほかの症状との比較も簡単です。診断書や紹介状などを作るのも早くできますし、悪筆な先生の文字が読めない……ということもなくなりますよね。 薬の処方や、検査をオーダーするときの間違いもなくなります。大きな病院ではネットワークで記録を呼び出せますから、ちがう科で診察する先生も、その記録をすぐ参照できるわけです。さらに、会計まで事務処理がスムーズにすすみます。 ただし、まだどの病院でも利用できるような業界標準のシステムやフォーマットはできていないのだそうです。たしかに、病院や科による診察のちがいもあれば、お医者さんのITスキルもいろいろ。それに、紙への自由な書き込みに比べると、自由度が低かったり、情報量が少なかったり。システムがマヒしてしまうような災害時や停電の時には使えないとか、データの書き換えや改変が簡単といった問題点もあります。発展途上なんですね。 とはいえ、将来的に電子カルテのシステムがいきわたれば、どこの病院で受診しても、予約して待ち時間を減らしたり、病歴を確認できたり、飲み合わせの悪い薬を避けたりできるようになるわけです。患者の私たちにとってもいいことがたくさんありそうです。命にかかわることですから慎重に、ですが一日も早く実現して欲しい仕組みですね。
|
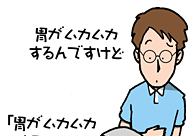 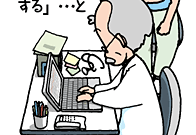
|