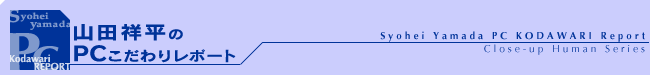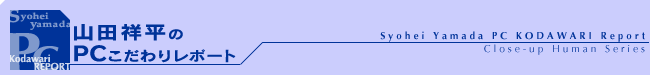| |
|
| |
米沢のチームが新LaVie Cに投入した叡智はまだたくさんある。たとえば、それは、ワイヤレス技術だ。同機では、競合他社製品に比べ、きわめて安定した無線通信が可能だ。アクセスポイントからの距離によって、転送レートを落とす802.11bの仕様において、他機種が39m離れた時点で5.5Mbps、60mで2Mbpsになるのに対し、LaVie Cでは、100mの距離においても11Mbpsを実現する。
このパートを担当したのは、チームの紅一点、阿部(NECカスタムテクニカPC事業部商品開発部)だ。
 「アンテナをつけることで、感度が向上することはないんです。ロスを抑えるのが重要なんですね。アンテナが持っているスペックを最大限に発揮させ、電波を集める力を生かせるように配置します。それが、モジュールの性能を最大限に生かすことにつながります。 「アンテナをつけることで、感度が向上することはないんです。ロスを抑えるのが重要なんですね。アンテナが持っているスペックを最大限に発揮させ、電波を集める力を生かせるように配置します。それが、モジュールの性能を最大限に生かすことにつながります。
モジュールからアンテナまでの配線ルートを気にしましたね。距離を短くするという工夫です。アンテナの位置を変えながらシグナルとノイズの影響を測定して搭載位置を決定します(図1)。製品アセンブリの点ではパネル側にアンテナをおくほうがいいんですが、そうすると、ヒンジのところを配線が通ることになり、強度の点で不安が残ります。でも、そこはメカの腕の見せどころに期待しました。
日本のアンテナベンダーはセラミックや基板などで小型化の工夫をしているところが多いです。海外(台湾)のベンダーは簡単な作りですが、装置によっては安く、性能良く載せられるので、装置によって使い分けをしています」
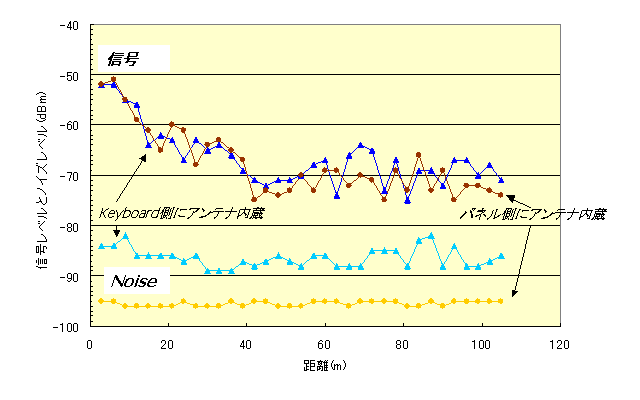 |
| [ 図1 ] |
アンテナは最終的に液晶パネルの上部両脇に位置させることになった。来るべき802.11aの時代に備え、高い周波数にも対応できるように考慮した結果だ。近い将来、LaVieが11aワイヤレスに対応するときも、アンテナを変更するだけですむという。いったんは、上部の黒いアクリル部分に搭載することも考えられたが、製品ではその外側、ちょうど右上端、左上端にダイバシティアンテナが埋め込まれている。
「無線の実験環境でもっとも困るのは、同じ環境を作ることができない点です。温度、時間などで、測定結果がどんどん変わってしまうんです。特に米沢の冬は雪が降りますから、たいへんです。本当に100メートルの電波暗室があったら、どんなにいいかと思います。無茶なんですけど(笑)。
ただ、パネル側にアンテナを持ってきたことで、実証実験の効率はよかったです。パネルの構造が変わることは少ないので、新しい試作機ができてきたら、データがまるで違うということがありませんから」
阿部は、アンテナが、標準化とは逆行するパーツであるという。そして、今後は、アンテナを見せるデザインも考えなければならないかもしれないと考えている。5GHz帯を使うようになれば、ユーザーがアンテナの場所を意識した方が、よい結果を得られるようになるからだ。また、携帯電話がそうであるように、日本では、アンテナが見える方が好まれる文化があるかもしれないと阿部は分析する。
しんしんと雪の降る米沢で、かじかむ手をこらえながら、LaVieを抱えて繰り返された実験が突出した安定度を生んだ。
 LaVie
Cの上位機種では、15型のUXGA液晶パネルが採用されている。ノートパソコンに搭載されたものとして、画品質世界一を自負する。実機を見ると、若干の赤みを感じるが、黒が黒く、高コントラストで画像がしまって見える。もちろん、視野角も広く、見る角度がずれても色が反転することがない。色味に関しては、徹底的に作り込んだICCプロファイルを提供してもらえれば解決する話だ。その対応に期待したい。このパートの担当は対間(NECカスタムテクニカPC事業部商品開発部)だ。 LaVie
Cの上位機種では、15型のUXGA液晶パネルが採用されている。ノートパソコンに搭載されたものとして、画品質世界一を自負する。実機を見ると、若干の赤みを感じるが、黒が黒く、高コントラストで画像がしまって見える。もちろん、視野角も広く、見る角度がずれても色が反転することがない。色味に関しては、徹底的に作り込んだICCプロファイルを提供してもらえれば解決する話だ。その対応に期待したい。このパートの担当は対間(NECカスタムテクニカPC事業部商品開発部)だ。
「この液晶パネルは、IPS(in-plane-switching)という技術で作られています。従来のTN液晶は、一個一個の液晶が縦に並んでいたため、光がねじれ、光軸を一本しか確保できませんでした。今までの液晶で、斜めの限られた角度から見たときだけに、最良の視認性が確保できていたのはそのためです。今回のパネルでは、液晶を横に並べて光の通り道を確保した結果、視野角が大きく広がっています(図2)。
また、従来の液晶は、ガラスとガラスの間の距離を均一に保つために、スぺーサーと呼ばれるボールを入れていました。ボールの近くには液晶材がないので、光がそこを通り抜けてしまい、出したい黒が明るくなってしまうんです。そこで、画素をスイッチングするためのトランジスタの上に柱をたてて、光が抜けないようにすることで、黒が黒く見えるようにしています。トランジスタを作るときに、柱スペーサを埋め込んでしまうんですよ(図3)。
このパネル、去年の秋にはすでに世に出ていたんですが、白が緑っぽいことと、表示に多少のムラがあったことで採用を控えていました。最初に、ベンダーから届いた試作機を見ると、右下と左下が暗かったんです。もちろんクレームで改良を求めましたが、なかなかそれが理解してもらえませんでした。どうしてこのムラがわかってもらえないのか不思議でしたよ」
対間は、画質に徹底的にこだわった。右下と左下が暗かった表示を回避するために、導光板に工夫し、レンズメッシュの入れ方を変えた。また、CFLランプに入っているガスの分量を調整し、白を白に見えるようにしたという。完成までに金型を4つお釈迦にしたというから、その徹底ぶりがわかる。
また、この液晶パネルは常時輝点がない点も特筆しておかなければならない。製品中8割はドット欠陥がなく、残りの2割に、1〜10個程度の欠陥があるが、それらは配線を切ることで黒になっているため、ユーザーが気がつくことはまずないという。1枚のパネルの検査に1分以上の時間をかけ、座標と回路を調べる機械の力を借りた手作業で、配線切断をすることで実現された目に見えない部分のスペックだ。この地味な努力がユーザーの満足度につながっていく。
対間はデモのために並べられた各社のノートパソコンの中でも、ひときわ美しい液晶パネルを持つLaVie Cを眺めてつぶやいた。
「せっかくなんだから、もっと液晶の美しさがわかるような壁紙にしてくれればいいのに」
それぞれの想いが新LaVie Cにこめられている。 |
|
|
|
|