| |
 |
|
秋田産の大豆を能代市内の農家から集めた稲ワラで包んで作る桧山納豆は、ネバネバ感と大豆のかみ応えがほどよく調和した昔ながらの素朴な納豆である。通気性の高いワラつとで包むことによって、時間がたつと大豆が次第に固くなり、ワラつと納豆ならではの歯応えが生まれる。それでいて大豆の甘みもしっかり残っている。昔ながらの知恵が詰まった伝統食である。 |
|
| |
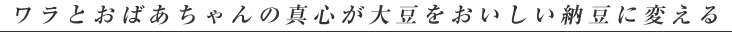 |
江戸時代初めに作られた『秋田音頭』に、「秋田名物 八森ハタハタ
男鹿では男鹿ブリコ 能代春慶 桧山納豆 大館曲げワッパ……」と唄われた桧山納豆。
糸がしっかりからみついた大豆はやや硬めの舌触りだが、かみしめればほっくりした大豆の感触が奥歯を通して伝わってくる。確かな記録は残っていないが、能代市の桧山地区に納豆作りが伝わったのは、今から約450年前のことという。茨城県の水戸から桧山城主とともに移ってきた人物が納豆の製法を広めたとの説が有力だ。明治期には秘法として伝えられてきた製法を受け継ぐ3軒の製造元があったが、今では1軒のみ。その製法を見たくて、桧山納豆製造元を訪ねてみた。 |
 |
|
| |
 |
 |
 |
| |
| 大豆の蒸し時間は1時間ほど。圧力釜を使い、その日に使う分は朝7時ごろから蒸しはじめる。蒸しあがったら霧吹きのような機械で納豆菌をふりかける。すべての粒に納豆菌がゆきわたるよう、均一にかけることがポイント |
|
民家に混じって「元祖桧山納豆」の看板を掲げる製造所に着いたのは、朝8時前。14代目の西村庄右エ門さんが、圧力釜の前で大豆の蒸し具合を確認していた。傍らでは、ワラを熱消毒する機械から勢いよく蒸気が噴き出ている。「もうすぐ作業が始まりますから」と西村さんがつぶやくと、近所のおばあちゃんたちが真っ白な作業着に身を包んで三々五々集まってきた。
「それじゃあ」と、西村さんが釜から大豆を籠に移す。大豆は、すかさず納豆菌を振りかけられて作業場へ。待ち構えていた8人ほどのおばあちゃんが、流れ作業でワラつとに大豆を詰めてゆく。おたまですくってワラつとに大豆を盛る人、ワラつとを閉じてワラのひもで結ぶ人。「大豆が温かいうちに手際よく詰めることが、ほどよく発酵・熟成させるためのポイント」と西村さん。まるで機械のようにリズミカルな作業が続き、見る見るうちに大豆を詰めたワラつとができあがってゆく。あとは室(むろ)に20〜21時間ほど入れておいて、発酵・熟成を待つだけ。現在の室は、完全な機械管理。経験に基づいた温度管理を自動で行い、均一の品質の納豆ができるのだ。温度の上げ具合、冷まし具合によって納豆の味が違うとういうのだが、詳細は企業秘密とか。 |
|
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| 城下町としての歴史がある桧山の集落にただ1軒だけ残っている納豆製造元だ |
14代目主人の西村庄右エ門さんは74歳。終戦直後から奥さんとともに納豆作りに取り組んできた |
大豆を盛ったワラつとを手際よく閉じてゆく。この工程はすべて手作業。近所のおばあちゃんたち8人ほどで作業を行い、週に約4500本を作る |
|
| |
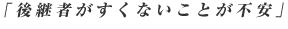 |
| 集落内の別の場所にある、ワラつと作りのための小屋も見せてもらった。ここでも2人のおばあちゃんが、もくもくとワラつとを作っていた。桧山のワラつとは、他に比べてやや短いことが特徴。作り方は、西村さんが直々に伝授しているという。
「最近はテレビで紹介されたり、自然食が見直されていることもあって全国から注文が増えている。うちは、近所の人の人手が頼りの家庭内手工業みたいなもんだから、以前はのんびりやっていたけれど、生産が追いつかないこともあって」と、うれしい悲鳴も漏れる。「稲ワラの確保が困難になりつつあり、ワラつとを作る後継者が少ないことが不安」とも。それでも、納豆本来の味を楽しんでもらいと、ワラつと納豆にこだわり続けている。 |
 |
| |
| ワラつと作りは、ワラを保管している専用の小屋で行われている。ここでも作業の主力はおばあちゃんたちだ |
|
|