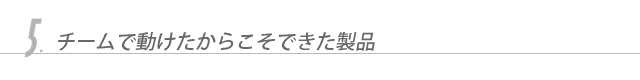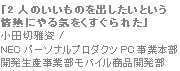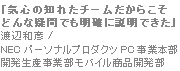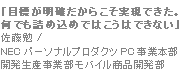保谷と丸川は、今回のプロジェクトは、ひとつのチームとして最初からうまく動いていたのがラッキーだったと述懐する。米沢では、メカ担当の佐藤勉、スケジューリング全体を見る渡辺和彦、そして、マネージャの小田切雅資が関わった。
| 小田切 |
「自分は前のプロジェクトを終わって途中からこのチームに入りました。保谷や丸川は、同じことを、もう一度説明しなければならなかったので、たいへんだったと思います。でも、いいものを出したいと、めざすところはいっしょなんですね。だから、話しているうちに、情熱が伝わってきます。そして、美しさに対する追求を感じました。人間、あるものを見たときに、できるわけがない、やりたいというふたつの気持ちに分かれると思うんです。この装置の場合は、話を聞いていて、やりたいという気持ちになりました。ツヤを出したいというだけなら、適当にごまかすんですが、深みを出したいとかいうんですよ。だから、細かいところまでを考えているのがわかりました。ユニバーサルデザインに関することも、ちゃんとやろうとしています。これは、生半可なことはできないぞと、とても強く感じましたね。たいていの企画は、パワーポイントで作った資料でサッと説明されておしまいですから」 |
| 保谷 |
「半端なコミュニケーション量じゃなかったです。このチームは、とにかくいっていることを頭から否定することはありませんでしたから、相談しやすかったです」 |
| 渡辺 |
「保谷さんとは、LaVie
Nもいっしょにやっていたので、そのバックグラウンドはだいたいわかっていましたから、なんでこんな要件にするんだと小田切さんにきかれるたびに、明確に説明することができました」 |
| 小田切 |
「装置が使われるシチュエーションを説明してもらったときに、そこから、すべてが見えました。企画として、要件として完成されているんですね。普通は、要件を見て、そこから、新たな提案をするんですが、ほとんど網羅されていました。やる気をくすぐられる説明をしてもらったということですね」 |
| 佐藤 |
「製品のコンセプトがはっきりしていたので、目標が定めやすかったんじゃないでしょうか。つまり、何を求めているかがはっきりしていたわけです。何でもいいから機能を詰め込めということでは、こういう装置はできません」 |
保谷と丸川のパソコンは、生産は上海で行われるが、いわば半完成の状態で日本に輸入され、いったん米沢でアセンブリしての出荷となる。だから、胸をはってメイド・イン・ジャパンの製品として世に出て行く。彼女たちのコンセプトは、いったいどんなカタチになるのだろう。彼女たちにできることは、もうない。 |