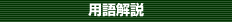 |
 |
レンズにより結像された画像の光量をデジタル信号に変換する素子。基本的にはフィルムと同様のシステムで、光の三原色それぞれの強弱を電子化してデジタルデータとする。フィルムのハロゲン化銀粒子に相当するのが一般的に画素と称されるもので、画素数が多いほど記憶データ量が多くなり、精細な画像を再現できる。また、撮像素子の大きさはいろいろで、コンパクト・デジタルカメラには1/3.2型、1/2.5型、1/1.8型(6.9×5.2mm)などの小さなものが多く使われている。撮像素子が大きいほど、画像の再現性や感度などの点で有利になる。構造的にいくつかの種類があり、デジタルカメラにはCCDやCMOSと呼ばれる撮像素子が多く使われている。
|
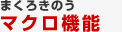 |
近接撮影機能のこと。コンパクト・デジタルカメラに装備されているレンズは、通常は50センチ程度の距離までしかピントが合わないが、マクロ機能を使えば、もっと近距離の被写体を写すことが可能になる。言い換えると、小さな被写体でも近寄って、アップで写せるようになる。スイッチで通常撮影とマクロ撮影とを切り替えるタイプが多い。
|
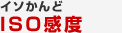 |
写真フィルムが光を感じる速さ(スピード、感度)を表す単位。デジタルカメラではフィルムではなく撮像素子なので、ISO100相当と表記されることが多い。感度が高い(数字が大きい)ほど弱い光にも感じやすいので、暗い場所でも速いシャッターを切れることになる。
|
 |
フルカラー静止画像を高い圧縮率(画質)で処理する形式。画像が小さくできる。
|
 |
デジタルデータを記録する媒体のことで、CD、MO、DVD、FDなど多種多様なものがある。デジタルカメラのメモリーカードもメディアの一種。
|
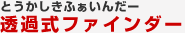 |
フィルム用のコンパクトカメラに通常装備されている、のぞき窓状のファインダーのこと。のぞくと、撮影範囲を示すフレームが見えるようになっており、明るく、見やすいのが特長。しかし、実際に写すレンズを通して被写体を見ているわけではないので、ファインダーで見た被写体と写した画像とにズレ(視差)が生じる。近距離の撮影ほど、この傾向が強くなる。この欠点を解決したのが一眼レフで、撮影レンズを通した画像をファインダーで見られるので、視差がない。
コンパクト・デジタルカメラの透過式ファインダーは、ほとんどが撮影範囲を示すフレームを省いた簡易型なので、視差がより大きくなりがちだ。これは、液晶モニターを使って撮影することを重視した設計で、ファインダーは補助的に考えられているからだ。
|
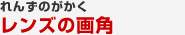 |
レンズで写せる範囲のことを画角という。これは、レンズ前面の何度の範囲が写せるかという意味。この画角は、レンズの焦点距離(ズームだと○○mm〜□□mmと表示される)と撮像素子の大きさで決まってくる。そのため、同じ焦点距離のレンズを使っても、撮像素子の大きいデジタルカメラほうが画角が広くなる。そこで、デジタルカメラの場合には35mm判フィルムカメラに換算してレンズの画角を表記するのが一般的だ。
|
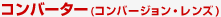 |
コンパクト・デジタルカメラのレンズは固定されており、交換できない。そこで、焦点距離を変換するためにレンズ前面に装着する補助レンズがコンバーター。レンズをより広角にするのがワイドコンバーター、より望遠にするのがテレコンバーター。カメラメーカーの純正品とアクセサリーメーカーの汎用品がある。ただし、デジタルカメラの機種によって装着できるものとできないものとがあるので、確認が必要。
|
| |